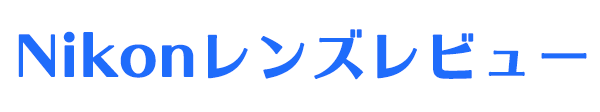運動会レンズのおすすめ、選び方と使い方、シーン別運動会撮影のコツとは?
運動会撮影に最適なレンズとは?NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRで最高の思い出を残そう

プロカメラマンがおすすめする運動会撮影に最適なレンズとは?
ニコンの超便利ズームである NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRが運動会撮影レンズとして最高に使い勝手が良いので、レンズの魅力や、運動会の様々なシーンでの撮影のコツも含めてお伝えしようと思う。
関連記事: NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR レンズ レビュー
24-200mmレンズを運動会撮影レンズと使用するメリット、デメリット
焦点距離24-200mmで運動会撮影に必要なシーンをカバーできる
標準ズーム+望遠ズームなど2本のレンズを使用して撮影する場合はレンズ交換や(2台のカメラを使って撮影する場合も)カメラのボディー持ち替えなどに時間がかかってしまうが、NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRなら1本のレンズに24-200mmの焦点距離が含まれているのでレンズ交換ボディー交換の必要なく、シャッターチャンスに圧倒的に強いというメリットがある。
軽量コンパクト設計で撮影が楽
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRは重さ僅か570g、レンズの長さ114mmと小型軽量なので身体にも優しい。
24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8を付けたカメラボディー2台体制で撮影するのと比較すると総重量は1/3程度になるだろう。
スクールフォトを撮影するプロカメラマンにとって、中学、高校の体育祭撮影日は(学校により)早朝から夕方まで続く長時間労働のため、機材重量が軽くなるのはありがたい。
高い画質・機能で素晴らしい写真を撮影できる
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRはズーム全域、画像中心から最周辺までシャープな解像力である。
このレンズを実際に使用するまでは、もっと解像力が甘いのではと思っていたが、実際に運動会撮影、遠足撮影などで使用してみたところ、解像力は十分以上であり全く問題無い。想定以上に解像力のあるレンズであることが分かった。
スクールフォトカメラマンの納品写真サイズは長辺2500ピクセル〜4000ピクセル程度なので画素数でいえば400万画素〜1000万画素である。この画素数の写真なら、大三元レンズで撮影するのと比較しても全く劣らない高解像度の写真を撮影できる。
ライバル会社のCANONはもう少し高倍率ズームのRF 24-240mm F4-6.3 IS USMというレンズを発売しているが、RF 24-240mm F4-6.3 IS USMを実際に使用しているプロカメラマンによると、卒業アルバムで使用する集合写真撮影時には少し解像力が足りないと話していた(1ページ全体のサイズで使用する場合)。
筆者はNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRを集合写真撮影でも使用してみたが、解像力は全く問題無いと感じている。
防塵・防滴である
急な雨が降り出したとしても多少の水濡れを心配することなく撮影を続けられる。
屋外で行われる運動会撮影では念のためカメラ用のレインカバーや折りたたみ傘も持って行くと、より安心だろう。
逆光に強い
一昔前の大三元レンズと比較しても逆光には強いと感じている。
レンズには最新のアルネオコートコーティングが施されていて反射防止効果があるという。
体育祭が終盤になり太陽が西方向に傾いてきた閉会式の撮影時も、多少の逆光撮影であってもゴーストやフレアーをそれほど気にせず撮影を行うことができる、最高のレンズである。
VR(手ブレ補正)機能がついている
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRは手ブレ補正効果5.0段※のレンズシフト方式VR機構を内蔵している。
望遠側の開放絞りがf/6.3と少々暗めでも、5段手ブレ補正により手ブレを抑えながら撮影することができる。
安い、安すぎる
こんなに高性能で小型軽量なのに11万円くらいで購入できてしまうこの安さ。
24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8の大三元レンズ2本を購入しようとすると合計50万円以上かかってしまうのに、NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRならその4〜5分の1の価格で24-200mmの焦点距離のズームレンズを手に入れることができる。
最高のコストパフォーマンスである。
良いカメラを持っている人なら、NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRが1本あるだけで、スクールフォト撮影アルバイトですぐにレンズ購入資金を回収できてしまうだろう。
運動会撮影だけでなく、旅行用、登山用、遠足撮影にもおすすめ
小型軽量なので、運動会撮影だけでなく、旅行、登山、遠足の撮影のも使い勝手の良いレンズである。
デメリット:僅かに開放絞りが暗いので室内撮影にはおすすめできない
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRは開放絞りがf/4〜f・6.3なので屋外撮影には全く問題無いが(屋外で行われる運動会撮影では通常f/8以上に絞り込んで撮影を行う)、体育館で行われる運動会や、室内スナップ時には若干開放絞りが暗いと感じる。
室内撮影には次のレンズがおすすめだ。
関連記事: NIKKOR Z 24-120mm f/4 S レンズ レビュー
一般的な運動会撮影でプロが使うレンズの組み合わせ例
運動会撮影用レンズの組み合わせとして過去に次の組み合わせで撮影を行ってきた。またはその組み合わせで撮影しているカメラマンを見てきた。
1.大三元レンズ運動会撮影セット
24-70mm f/2.8、70-200mm f/2.8を使いカメラボディ2台セットで撮影する手法である。
屋外で行われる運動会を撮影する際に、一般的に24mm〜200mmまでの焦点距離があれば運動会撮影に必要なシーンをカバーできる。
24mm〜200mmまでを撮影できる最高峰レンズがf/2.8通しの大三元レンズ
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
の2本の組み合わせである。お金があり、カメラボディも2台もっていて体力もあるなら上記2本の組み合わせで運動会撮影するのもおすすめである。
上記2本の大三元レンズは素晴らしい描写のレンズであるが、一般的な運動会撮影(写真販売用、卒業アルバム用、記録用)ではそこまでの描写性能は求められない。
2.便利ズーム+望遠ズームレンズ、運動会撮影セット
24-120mm f/4、70-200mm f/2.8のレンズを使いカメラボディ2台セットで撮影する手法である。CanonやSonyの一眼カメラを使用するなら24-105mm+70-200mmの組み合わせとなるだろう。
または、100-400mmレンズを持っている場合は、24-120mm、100-400mmレンズの2台セットで撮影しても良いだろう。
標準焦点距離領域の撮影に
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
を使うことにより広角から望遠までの焦点距離範囲が広がりカメラボディ持ち替え回数を減らせるというメリットがある。
さらに、もっと便利なレンズが今回紹介する次のレンズである。
3.便利ズーム1本、運動会撮影セット【一番おすすめ】
(Zマウントミラーレスカメラ利用の場合)NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、(Fマウント一眼レフ使用の場合)AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VRを使いカメラボディ1台で撮影する手法である。Canonのミラーレスカメラなら、24-240mmという高倍率便利ズームが存在する。
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
この超便利ズーム1本で、(屋外で行われる)運動会撮影に必要な全てのシーンを撮影できるのだ。
4.DXフォーマット(APS-C)機で撮影する場合の運動会レンズ
Canon機の場合、18-135mm(フルサイズ換算で24-200mm相当)。NIKON Fマウントの場合は18−140mm(フルサイズ換算で24-210mm相当)を使う選択肢もある。
運動会撮影に必要なレンズの「望遠側」焦点距離とは
運動会・体育祭撮影で必要な望遠側の焦点距離は200mmあれば十分
スクールフォトカメラマンが運動会撮影を行う場合、望遠側の焦点距離は200mmあれば十分である。300mmまであればなお良いが、400mmまではほとんど必要無い。
中学校、高校の体育祭撮影に必要な望遠レンズの焦点距離の目安
一般的な中学校、高校の広めの運動場(トラック一周200m)の場合、200mmレンズがあればトラック短辺方向の対面側の応援席1クラス分画面一杯に撮影できる。
またトラックの斜め方向直線に設置された100m走をゴール側から撮影する場合も、200mmレンズを使うことにより「スタート地点の選手全員」をほぼ画面一杯に撮影できる。
Nikon Z9などの高画素機を使ってDXフォーマット(APS-Cサイズ)クロップを行う場合は焦点距離が1.5倍相当の撮影ができるので、100m走のゴール側からスタート地点を撮影する場合に200mmの望遠レンズを使うことにより300mmレンズ相当の望遠レンズとして使えるので、数名をクローズアップして撮影できる(それが必要なシーンはほとんど無い)。
保育園、幼稚園の運動会撮影に必要な望遠レンズの焦点距離の目安
保育園、幼稚園の運動会を撮影する場合、ほとんどのケースで中学校や高校の運動場よりも狭い園庭で行われるので、中学校、高校の体育祭の撮影すると望遠側の必要焦点距離は短くなる。
園庭で行われる運動会を撮影する際に最も撮影距離が長くなるのが園庭の長辺方向を走る徒競走をゴール側からスタート地点を撮影するシーンである。
一般的な園庭の直線徒競走なら、120mmレンズがあればゴール地点から狙ってスタート地点に並ぶ園児全員を画面一杯に撮影できる。
さらに、200mmレンズがあれば、ゴール地点から撮影してもスタート地点の園児1〜3名をクローズアップして画面一杯に撮影できる。
園庭のトラックを一周するリレーを撮影する際に、スタート・ゴール地点の前方のコーナー外側から撮影すると、24-200mmレンズがあれば、ゴール地点、バトントス地点の園児をほぼ画面一杯に撮影しつつ、第一コーナーを走る複数園児数名を(広角側最大24mmで)1枚の写真に収めることができる。
運動会撮影に必要なレンズの「広角側」焦点距離とは
運動会・体育祭撮影で必要な広角側の焦点距離はできれば24mmまで欲しい
一般的な運動会撮影で使用するズームレンズの広角側の焦点距離は24mm(24-70、24-120、24-200mmmなど)または28mm(28-300mmなど)となる。
24mmと28mmレンズの焦点距離はたった4mmしか違わないが、広角側では少しの焦点距離の違いが大きな画角の違いとなる。
24mmと28mmレンズの画角の違いは次の通りである。
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角線画角 |
|---|---|---|---|
| 24mm | 73.7度 | 53.1度 | 84.1度 |
| 28mm | 65.5度 | 46.4度 | 75.4度 |
保育園・幼稚園の運動会撮影なら24mmレンズまでの広角レンズが欲しい
保育園・幼稚園の園庭で行われる運動会の場合、(中学校や高校の運動場と比較すると)園庭が小さめのことが多く、トラックを回るリレー競技を第一コーナーの外側から撮影する場合、カメラ位置と園児までの位置が非常に近くなることがある。
(28mmでなく)24mmまでの広角があればより広い範囲を撮影できるので園児の全身を撮影したり、または複数園児を1枚の写真に撮影することができる。 一般的に販売用写真を撮影する場合は1名が写る写真よりも複数名が写る写真の方が求められる。写真が売れやすい、売上げが上がるため、一人が写る写真よりも複数名が写る写真の方が、他の園児との関係性が分かるため。
中学、高校の体育祭を撮影する際もできれば24mmレンズまでの広角レンズが欲しい
トラック側から応援席側を撮影する際、応援席のすぐ前にしゃがんで応援する生徒を撮影するシーンで、24mmあれば3〜5名の生徒が手を上げて応援する様子を迫力ある画面一杯の広角写真に収めることができる。
トラックの内側からリレー選手を撮影する際も、28mmよりも広角な24mmレンズで撮影することにより、目の前を走る選手を迫力ある写真に収めることができる。
望遠側の焦点距離の長さよりも、広角側の焦点距離の短さの方が重要である
望遠側はクロップ、トリミングすることにより実質焦点距離を伸ばすことができる。
FX⇒DXフォーマット(フルサイズ⇒APS-Cサイズ)にクロップすることにより実質焦点距離を1.5倍にできるので、遠側は200mmレンズで撮影したとしても300mmレンズで撮影したと同等の画角の写真を撮影できる。
一般的なスクールフォト撮影では、納品写真サイズが長辺サイズ2500〜4000ピクセル程度のため、高画素機(4500万画素のNikon Z9など)で撮影した場合に目一杯トリミングすることにより200mmレンズで撮影した写真を400mm〜最大600mmレンズで撮影した画角まで拡大することができる。
しかし広角側はファインダーで見える範囲の外側を写すことができないので、3名が写る写真をその外側の生徒まで含めて5人が写る写真にしたい、のように画角を広げることはできない。
だから、広角側は24mm程度の広角レンズが欲しい。
広角側があれば、近くから撮影するとより迫力ある写真を撮影できるが、24mmあれば十分であり、20mm、14mmなどの広角レンズはほとんど必要とされるシーンがないので、広角ズームや単焦点20mmレンズを付けたもう1台のカメラを持つことにより機動力が落ちてしまうメリットを考えると、24mm〜スタートのズームレンズがあれば必要十分である。
運動会撮影に必要な納品写真画素数基準の目安
筆者は複数のスクールフォトエージェントや卒業アルバム制作会社に登録し、運動会シーズンには毎週数件の運動会撮影を行っている。
運動会撮影した写真の納品サイズ基準は各社により若干異なるが、写真販売用の場合は、Lサイズでプリントして販売するので写真データサイズは「長辺2500ピクセル、画像サイズ2MB以下」が基準となる。画素数で計算すると
(長辺)2500 × (短辺)1667ピクセル = 416万画素
である。
卒業アルバム用のスナップ写真は若干大きめのサイズが求められる会社もあり、筆者が登録しているアルバム制作会社では各社別に「長辺2500ピクセル、2MB以下」「長辺3500ピクセル、3MB以下」「長辺4000ピクセル、3.5MB以下」というサイズで納品している。その中でも最も画素数が大きい「長辺4000ピクセル」で画素数を計算すると
(長辺)4000 × (短辺)2667ピクセル = 1066万画素
のサイズになる。
トリミング想定で考えると実質焦点距離を上げることができる
納品写真サイズが小さいということは、高画素機で撮影しトリミングを行うことにより(撮影写真の一部を切り取って使うことにより)、実質焦点距離を望遠側に大きくすることができる。
例えば、4544万画素(8256×5504ピクセル)のNikon Z9で焦点距離200mmレンズで撮影して長辺4000ピクセルまでトリミングを行うと、約400mm相当のレンズで撮影した画角と同等になる。
つまり、納品写真サイズが長辺4000ピクセルの場合、Nikon Z9+200mmレンズで撮影すると、トリミングを行うことにより最大約400mmの望遠レンズで撮影したと同等サイズまで拡大撮影できる。
焦点距離別撮影画角
焦点距離別に撮影画角を計算してみた。
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角線画角 |
|---|---|---|---|
| 24mm | 73.7度 | 53.1度 | 84.1度 |
| 28mm | 65.5度 | 46.4度 | 75.4度 |
| 50mm | 39.6度 | 27.0度 | 46.8度 |
| 105mm | 19.5度 | 13.0度 | 23.3度 |
| 120mm | 17.1度 | 11.4度 | 20.4度 |
| 200mm | 10.3度 | 6.9度 | 12.3度 |
| 240mm | 8.6度 | 5.7度 | 10.3度 |
| 300mm | 6.9度 | 4.6度 | 8.2度 |
| 400mm | 5.2度 | 3.4度 | 6.2度 |
24-200mmレンズが運動会撮影レンズとして便利すぎる理由
スクールフォトカメラマンが運動会・体育祭撮影を行う際、できるだけバリエーション多い写真納品が求められる。
目の前で応援する選手を広角レンズで撮影したり、ゴール地点からスタート地点の選手・走ってこちらへ向かう選手を望遠レンズで撮影したり、目の前で競技する組体操選手を次々と撮影したりする。
「24−70mm+70-200mmレンズ」を装着した2台のカメラで撮影する場合、24mm広角から200mm望遠まで撮影する際焦点距離の違いによりカメラを持ち帰る必要があるが「24-20mmレンズ」を付けた1台のカメラボディで撮影すればカメラを持ちかえることなく、次々と撮影することができシャッターチャンスに強くなる、撮影枚数を多くできるというメリットがある。
「24−120mm+70-200mmレンズ」の「便利ズーム+望遠ズーム」の2台体制で撮影する場合は標準域の焦点距離が「24-120mmm」までと広いので「24−70mm+70-200mmレンズ」の2台と比較するとカメラを持ち帰る回数を少なくはできるが、それでも120mmで足りないシーンは多くあり、120mmで撮影して後からトリミングすると撮影後の作業に手間がかかり、「70-200mm」に持ち帰ると持ち帰る手間がかかる(機動力が落ちる)ので、やはり「24-200mm」レンズでの撮影は圧倒的に便利であると感じた。
Canon 24-240mmレンズとNikon 24-200mmレンズとの比較
ニコンZマウントの高倍率ズームレンズNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRと比較すると、CanonのRFマウントにはRF24-240mm F4-6.3 IS USMというニコンよりもさらに望遠側が240mmまでと僅かに望遠側が長くなるが筆者がNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRを使った感想としては、24-200mmレンズで必要十分であるという感想である。
現場でCanon R6+RF24-240mm F4-6.3 IS USM、Canon R3+RF24-240mm F4-6.3 IS USMを使っている2名のプロカメラマンにレンズの使い勝手をヒアリングしてみたところ、1名のカメラマンは「RF24-240mmは1本で撮影できるので便利」という意見であったがもう1名のカメラマンは「RF24-240mmは描写性能が若干劣るのでアルバム写真撮影で1ページ全体で使用する集合写真撮影には使えない(別レンズで撮影する)」という意見だった。
筆者を含めて「NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR」一本のレンズで運動会撮影、遠足撮影などを行っているカメラマンを知っているが自分も含めて「NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR」のレンズをべた褒めしている。
24-200mmレンズ1本で、カメラを持ち替えることなく全てのシーンを撮影できる
広角から望遠まで、24-200mmレンズ一本で撮影することができる。直線コースを走る選手や園児を撮影する際も24-200mmレンズが1本あればスタート地点からゴール地点までカメラを持ち替えることなくこれ一本で撮影できる。
集合写真を行う際もNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRで十分の描写性能で撮影できる。
さすがのNikkor Zマウントレンズである、若干の逆光シーンを撮影する際もNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRで大きなゴーストやフレアがでることは少なく、一昔前のFマウント大三元レンズと同等の撮影品質である。
運動会撮影する際のおすすめ設定
VR(手ブレ補正)設定はスポーツモードで撮影する
運動会撮影は動き物撮影なので、VR(手ブレ補正)設定は、静止画モードでなく、スポーツモードで撮影する。
VR静止画モードで撮影すると、1ショット毎にレンズが中央位置にリセットされるので、動く被写体を次々撮影する場合ファインダー内がカクカク表示になってしまうことがある。 動体撮影、連写撮影する場合はスポーツモードで撮影する必要がある。
AFモードはコンティニュアスAFに設定する
コンティニュアスAFで撮影することにより、遠くから手前に向かってくる選手を連写する場合も常にフォーカスを合わせながら撮影するとができる。
徒競走撮影リレー撮影など、複数選手をZ9撮影する際はカスタムワイドエリアAFが便利
Nikon Z9で複数選手を撮影する場合は、カスタムワイドエリアAFが便利である。
徒競走やリレーのゴールシーンを撮影する場合など、カスタムワイドエリアAFの水平方向を最大、垂直方向サイズを1〜2枠に設定することにより、手前にゴールテープ、その奥に複数選手がこちらを向かってくる場合に手前のゴールテープにAFが合焦することを防ぎつつ、横に並んで向かってくる選手のうち一番カメラに近い側の選手にフォーカスを合わせることができる。
動く選手を撮影するには3D-トラッキングAFが便利
Nikon Z9、Nikon D6、D850の3D-トラッキングAFなら狙った選手が上下左右に動いてもフォーカスが被写体を追い続けてくれる。
状況に応じて被写体認識をOFFにして撮影する
人物認識をONにすると被写体の顔にAFを合わせることができるが、横方向に走る選手の奥にこちらを向いて応援する選手がいる場合に走る選手でなく、顔をこちらに向けている奥の選手にフォーカスが合ってしまうことがあるので、運動会撮影において筆者は人物認識機能をOFFにして撮影している。
この設定はカメラマンによって好みが分かれるので実際に撮影してご自身の良い設定で撮影するのが良いだろう。
もし、狙った手前の選手でなく奥の人物にフォーカスが合ってしまうと感じた場合は被写体認識をOFFにすることにより改善される可能性がある。
露出モードはマニュアル露出で撮影することが多い
逆光気味で撮影する場合にシャッタースピード優先、または露出優先露出にすると選手の顔が暗めに写ってしまうことがあるので、急激な天候変化がない場合、筆者はマニュアル露出で撮影することが多い。
マニュアル露出撮影を行うことにより、写真毎に露出値が上下しないので納品前の後処理で複数写真の露出補正を行う場合の処理も楽である。
シャッター速度は最低1/1000よりも速く、できれば1/1600よりも早い設定にする
走る選手を撮影する場合1/500などのシャッター速度で撮影すると被写体がぶれて写ってしまう。最低でも1/1000以上のシャッター速度を使い、通常撮影で1/1600以上の早さ、可能なら1/2000以上の早いシャッター速度で撮影することにより被写体ブレをふぐことができる。
絞り値はf/8〜f/13くらいを使用する
70-200mm f/2.8などの明るいレンズで撮影する場合も通常の運動会・体育祭撮影ならf/8以上に絞り込んで撮影することにより被写体をくっきりと写しつつ、背景がボケボケにならずに良い写真に仕上がる。
ベストな絞り値はf/8〜f/11程度である。
絞り値を最大絞る場合、晴天の場合もf/13〜1/16までにする。f/22など絞込過ぎてしまうと回折現象により、逆に全体的なぼけた写真になってしまうからだ。
また、f/16以上に絞り込むと、万が一センサーやレンズにゴミが付いている場合に写真にゴミが写り込んで(ゴミの形が見えたり、一部が少し暗く写ったりして)しまう場合がある。
撮影前にセンサーゴミを確認する
センサーゴミ、レンズゴミが付いた状態で撮影を続けると、納品前のゴミ消去処理が面倒になる、または写真品質が落ちてしまうので、できれば、撮影前にセンサーゴミの状況を確認すると良いだろう。
例えばA4サイズ、またはもう少し広めの白い紙を使って、24mm以上の広角レンズをf/16以上に絞り込んでフォーカスを無限園に合わせて机の上で2ショットカメラを少し左右に動かして撮影した写真をチェックしてみる。
カメラを動かして撮影した写真の全く同じ位置に黒っぽいゴミが写り込んでいた場合はセンサーゴミ、またはレンズに付着したゴミの可能性がある。
ブロアでセンサーゴミを吹き飛ばす、またはセンサー清掃を行う必要がある。
ニコンのサービスセンターにカメラを持ち込むことによりセンサー清掃できるが費用も手間もかかるので筆者はいつも自分でセンサー清掃している。センサー清掃に筆者は次の商品を使っているが自分で簡単に綺麗センサー清掃できるので便利でおすすめだ。
連写しすぎない
連写設定は早くても10コマ/秒程度に抑えておく。
カメラによっては15コマ/秒、20コマ/秒、30コマ/秒などの高速連写を売りにしている機種も存在するが、15コマ/秒以上の設定で高速連写すると撮影後のセレクト処理が大変になる。
経験上、10コマ/秒あれば(7コマ/秒、9コマ/秒でも十分)、リレー競技を撮影する際に複数選手全員が浮いた状態の形の良い写真を撮影することができる。
大縄飛び撮影時には、Nikon Z9やNikon D6を使えば選手全員がジャンプした一番高い地点の写真を1ショットで撮影することができる。
また高速連写し過ぎると、カメラやメモリカードの種類によっては途中でバッファフルになり途中で連写が止まってしまうことがあるので運動会撮影を行う前にカメラとメモリーカードの性能を確認しておくと良いだろう。
ちなみに、Nikon Z9なら、10/コマ秒撮影でメモリカードが一杯になるまで永遠と撮影し続けることが可能だ(途中で連写が止まってしまうことが無いので安心して撮影できる)。
三脚を使って集合写真撮影する場合、手ブレ補正機能をOFFにする
三脚を使って集合写真を撮影する場合は、VR(手ブレ補正)機能をOFFにする。三脚撮影でVRが大きな悪影響を及ぼすことは少ないが、VR機能をONしたまま撮影すると複数枚撮影した写真の位置が微妙にずれてしまう場合がある。
通常のスナップ撮影する場合はJPGのみ記録している場合も、集合写真撮影は撮影後のレタッチ耐性を上げるためにRAWも記録しておく(RAWのみ撮影、またはRAW+JPG撮影)。
十分な容量のメモリーカードとバッテリーを用意しておく
撮影中にメモリーカードやバッテリー不足による撮影続行不能を防ぐためにメモリーカードとバッテリーは十分な量を準備しておこう。
なお、運動会スナップ撮影は(連写撮影を多用する場合は)、通常のイベント撮影と比較するとバッテリーの減りは少なくなるので筆者の経験では、Nikon Z9を使って撮影する場合はフル充電したバッテリー2本があれば早朝から夕方まで行われる中学・高校の運動会を一日中撮影することができる(バッテリー1本ではぎりぎり足りないこともある)。
プロカメラマンなら
撮影ミスが許されないプロカメラマンなら、24-200mmレンズ一本で撮影する場合も撮影現場にサブ機を持って行こう(万が一機材トラブルが発生した場合もカメラを交換して撮影を続けられるために)。
また、メモリーカード不具合によるデータ破損を防ぐためにダブルスロットカメラが必須となるだろう。
運動会・体育祭、競技別撮影方法
主に、スクールフォトカメラマンが向けに各競技別に「プロに撮影をお願いして良かったとも思われる宇」撮影方法をわかりやすく解説したいと思う。もちろん、ご自身のお子様を撮影する際も記念になるような写真映えするような写真を撮影するコツも合わせてお伝えしたいと思う。
本当なら実際の撮影写真例を見せながら解説するとわかりやすいが被写体の個人情報、または依頼者との契約条件により写真をお見せすることができないので文章による解説となる。
広角〜望遠までをフル活用してバリエーション多く撮影する
同じような写真が並び過ぎないよう、広角〜望遠までをフル活用してバリエーション多く撮影する。
例えば、綱引きを撮影する際もアップ写真ばかり撮影せずに、綱引き全体、または、片側チーム全体が写る写真も撮影しよう。一人一人の人物の顔が判別できなくても全体の状況が分かる写真は良く売れる。
低い位置から撮影する
時に保育園児、幼稚園児を撮影する場合は園児の目線を基準に低い位置から撮影する。
大人の立ち位置から撮影すると見下ろした写真になってしまうが、しゃがんで低い位置から撮影することにより、園児達の目線で迫力ある写真を撮影できる。
中学生、高校生の競技を撮影する際も(全てではないが)低い位置から撮影することにより表情が見えやすくなり、また地面が近くなることにより迫力あるシーンを撮影できる。
三脚や一脚は不要、カメラを手持ちで撮影する
ビデオ撮影する場合はブレを防ぐために三脚を使用することもあるが、スチール写真を撮影する場合はカメラマン立ち位置を次々変更しながら動き回りながら撮影するので三脚や一脚は使わずに手持ちで撮影する。
競技する選手だけでなく、応援のようすも撮影する
応援シーンも喜ばれる写真である。リレー撮影時に振り向いて、カメラマンの後ろで応援する生徒を広角撮影したり、走る選手を撮影する合間に望遠レンズで遠くの応援席で応援する選手や園児達を撮影する。
リレー撮影時には、目の前を走る選手の奥でこちらを向いて応援する選手が写る写真も良い写真になるだろう。
リレー・徒競走など、走る競技の撮影方法、撮影のコツ
スタートシーン撮影のコツ
スタート前、全員が並んでいる様子を撮影。余裕があれば3〜4名ずつなどのバリエーション撮影しても良いだろう。
保育園・幼稚園の場合呼名(園児の名前を呼ぶ)シーンがあるので、名前を呼ばれて「はーい」と手を上げた瞬間、ジャンプした瞬間を撮影する。
「位置について、よーい」と言った時の様子を撮影する。小学生低学年以下・保育園・幼稚園児の場合はそれぞれ個性豊かな格好をするので記念になる写真が撮影できるだろう。
スタートした瞬間写真。一歩〜数歩前へ進んだ写真。
走っているシーン撮影のコツ
走る位置、カメラ位置により、選手の正面、斜め前、真横、場合によって後ろからの写真を撮影できる。
正面、または斜め前から撮影する場合はNikon Z9の場合カスタムワイドエリアAFを使うことにより、横方向に並んだ選手のうち、一番カメラに近い選手にフォーカスを合わせることができ絞り値をf/8以上程度に絞り込むことにより被写界深度内の複数選手にフォーカスを合わせることができる。
複数選手を撮影する場合は、10コマ/秒程度の高速連写を行うことにより、選手全体の表情が良い写真、全体の形の良い写真(例えば、全員の足が地面から離れて浮かんでいる写真など)写真をセレクトする。
スマホカメラではなかなか良い写真を撮影できないので、ここはプロカメラマンにお願いして良かったと思える写真を撮影すれば喜ばれることだろう。
バトントスシーン撮影のコツ
バトンを手渡した瞬間(二人の選手両方がバトンをつかんでいる写真)、かつ、二人の顔がこちらを向いて表情が分かる写真が良い写真とされる。
一般的に右利き選手の場合、右手でバトンを受け取ることが多いので、トラックの(内側ではなく)外側から撮影することにより二人の表情の写った写真を撮影できる確率が上がるだろう。
なお、(左利きなど)選手によっては左手でバトンを受け取る場合は、受け取る選手がカメラの向こう側を向いてしまい顔が見えないこともある。
ゴールシーン撮影のコツ
ゴールテープにフォーカスが引っ張られることがないよう、Nikon Z9やNikon D6ならカスタムワイドエリアAF、グループエリアAFを使うことによりAF枠を横長方向に設定し、複数選手にフォーカスが合うよう撮影すれば撮影が容易だ。
リレー競技撮影時のカメラマンの立ち位置
カメラマン1名のみで撮影対応する場合は次の立ち位置で撮影する。
- スタート・ゴール位置前方、トラックの外側 スタートシーン、バトントスシーン、走るシーンを撮影できる。撮影中にもう少しコーナー側に移動することにより、直線コースを正面に向かって撮影することもできる。
- 余裕があればトラックの内側へ移動して撮影する 走る選手を内側から撮影することにより、その奥で応援する選手を背景に写すことができる場合もある。トラックの外側、内側とカメラ位置を変えることにより全体写真のバリエーションを多くすることができる。
カメラマンが2名の場合は、メインカメラマンが上記位置、もう1名の(サブ)カメラマンがトラックの対角線側のトラックの外側から撮影する。
選手がトラックを半周するリレーの場合もメインカメラマンと対角線上の反対側から撮影することによりメインカメラマンが撮影できないトラックの向こう側を走る選手のバトントスのようすや走る様子を撮影できる。
カメラマンが3名の場合は、3人目のカメラマンはトラックの内側から撮影する。走る選手をトラックの内側から撮影したり、トラックの外側で応援する生徒達を撮影する。
競技開始前にスタート位置、ゴール位置を確認しよう
撮影開始前の打ち合わせ時などに、スタート位置、ゴール位置を確認しよう。
競技によっては、スタート位置とゴール位置が異なる場合があるからだ。
スタートシーン、ゴールシーン、ともに重要なシーンとなるので、できれば両方の写真を撮影しておきたい。
組体操の撮影方法、撮影のコツ
競技前にフォーメーションを確認しておく
例)3名(サボテン) ⇒ 3+3=6名(扇) ⇒ 6+6=12名 ⇒ 全体(大橋など)で組体操します。など、可能であれば事前に組体操の流れ、フォーメーションチェンジを確認することにより全体をもれなく撮影できるだろう。
販売用写真の場合、基本、全員を撮影することを目指す。
扇、ピラミッド、など組体操の種類によっては決めポーズが一瞬で終わってしまうことがあり、その間に次々と撮影対象を変えながらできるだけ多くのバリエーション写真を撮影する。
園児数・生徒数に対してカメラマン人数が少ない場合はまずは広角側で全体撮影を行うことにより写真に写っていない園児・生徒を減らしより多くの被写体を撮影することができるだろう。
カメラマンが複数居る場合は、右側、左側など撮影位置、撮影範囲を事前に打ち合わせすることにより効率良くチームで撮影を進める。
トラック内に入って良いか、トラックの外側から撮影するか、競技開始前に担当先生に確認しておこう。
大縄飛びの撮影方法、撮影のコツ
全員が一斉に撮影する場合は、基本的に、ジャンプした瞬間の写真を撮影する。
Nikon D6、Nikon Z9などのフラッグシップカメラを使う場合はファインダーを見ながら撮影してもワンショット撮影するだけでジャンプした瞬間を撮影できるはずだ。
大縄飛びに次々に選手が一人ずつ走ってきて一人ずつジャンプする競技の場合、同様にジャンプした瞬間を撮影するのが基本だ。
縄跳びを回すタイミングに呼吸を合わせてシャッターを切ると同じタイミングで次々と撮影しやすいはずだ。
なお、フォーカス遅れを防ぐために、絞りを絞り気味(f/11〜f/16)にして被写界深度を深めた増えてジャンプする瞬間の位置に合わせフォーカスロックを行いながらで撮影することもある。
筆者は、Nikon Z9、Nikon D6の右親指で操作する位置にある「AF-ON」ボタンを「AF-LOCK」機能にカスタマイズしている。必要に応じて「AF-LOCK」ボタンを押すことによりAFずれ、AF遅れを防ぐながら次々とタイミング良く撮影できる。
綱引きの撮影方法、撮影のコツ
ベストな撮影位置(カメラ位置)は縄の中央の目の前だ。先頭の数名〜5名程度の選手の上半身を狙い力を入れて引っ張る時の表情を狙って撮影する。同時に、少し離れて全ての選手を含めた写真も撮影しつつ、縄の先端に向けて歩きながら先頭から数名の選手をグループ単位で撮影していく。
カメラマンが2名居る場合は右側と左側で担当を分けて撮影を行う。
カメラマンが3名入る現場の場合は上記に加えて、3人目のカメラマンは全体を撮影したり、応援する選手の撮影を行う。
玉入れの撮影方法、撮影のコツ
玉入れのかご全体を入れようとすると、選手の顔が小さくなってしまうので、かごを含めた全体写真を撮影しつつ、かごをいれずに玉を持った選手、投げる瞬間選手数名の選手の上半身写真を撮影する。
プロカメラマンに運動会撮影をお願いする場合の相場の目安
シーズンによりプロカメラマン料金の相場が変わる。
運動会撮影のハイシーズン、閑散期とは
運動会撮影の1年で最も需要が高いのが9月中旬〜10月下旬の土日である。主に保育園、幼稚園の販売用写真撮影が行われる運動会のハイシーズンである。
保育園・幼稚園の運動会写真は販売目的で撮影することが多く、撮影枚数は多くまた写真が良く売れるのでその分撮影費用は高くなる。
9月中旬〜10月下旬の次に運動会が良く実施されるのが5月中旬〜6月上旬である。主に、中学校、高校の運動会が開催される。
中学校、高校の運動会撮影は筆者の感覚では販売用ではなく卒業アルバム用・記録用として撮影を行うイメージである。公立中学校など公立の学校は平等性の観点から写真は販売されないことが多い(家計の状況により写真を購入できる家庭と購入する余裕の無い家庭があるからだ)。アルバム用・記録用撮影のため、販売用写真と比較すると撮影枚数、納品枚数は少なめでその分撮影費用は低めになる
プロカメラマン、運動会撮影依頼の費用の目安
一般的なカメラマンに撮影を依頼する際の運動会撮影費用(撮影時間が3時間以内の場合)の相場の目安は次の通りである。
| 時期 | 曜日 | 料金目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9月中旬〜10月下旬 | 土 | 20000〜35000円 | 写真販売用。 雨天・中止は半額保証 |
| 日 | 18000〜25000円 | 写真販売用。 雨天・中止は半額保証 |
|
| 平日 | 15000〜20000円 | 写真販売用。 前日夕方までキャンセル費用負担無し |
|
| 5月中旬〜6月上旬 | 12000〜17000円 | アルバム用・記録用 | |
| その他 | 10000〜20000 | 販売用 |
撮影時間が3時間を超える場合は、その分追加撮影料金が発生する目安である。
上記相場表の下限料金近いカメラマンの場合は経験が少ないカメラマンであったり、APS−Cフォーマットカメラを使っている場合がある。
経験豊富なカメラマン、Nikon Z9やNikon D6などのフラッグシップカメラを使いこなしているカメラマンに依頼する場合上記上限金額以上の料金になる場合もあるだろう。
NIKKOR Z 24−200mm f/4-6.3 VR、最安値比較
関連記事
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S レンズ レビュー
├ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S、開梱レビュー
└ NIKKOR Z 24-70mm vs 24-120mm vs 24-200mm を比較
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR レビュー
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S レンズレビュー
NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レビュー
Nikon Z9 レビュー
Nikon Z8 レビュー
Nikon Z6ii レビュー
Nikon D6 レビュー
関連リンク
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR (ニコン公式ページ)
Nikon レンズ レビュー、記事一覧
■新着記事
NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レビュー
└ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR、開梱レビュー
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S レビュー
└ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 vs 70-200mm f/2.8を比較レビュー
■便利ズーム
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S レビュー
├ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S、開梱レビュー
├ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S、仕様・スペック 徹底レビュー
└ NIKKOR Z 24-70mm vs 24-120mm vs 24-200mm を比較
NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR レビュー
└ 運動会撮影に最適なレンズとは?NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRで最高の思い出を残そう
NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズ レビュー
└ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR、開梱レビュー
■大三元レンズ
NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S レビュー
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S レビュー
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S レビュー
■ズームレンズ
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S レビュー
└ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 vs 70-200mm f/2.8を比較レビュー
■単焦点レンズ
NIKKOR Z 50mm f/1.2 S レビュー
NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 レビュー
NIKKOR Z 85mm f/1.2 S レビュー
└ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S 外観レビュー
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S レビュー
├ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S、開梱レビュー
├ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR SのYouTube動画一覧
├ NIKKOR Z MC 105mm vs NIKKOR Z MC 50mmを比較
├ NIKKOR Z MC 105mm vs AF-S MICRO-NIKKOR 105mmを比較
└ NIKKOR vs CANON 最新中望遠マイクロレンズ比較
■レンズ関連
NIKONキャシュバックキャンペーン2022 秋冬がお得すぎる件
└ NIKONキャシュバックキャンペーン 応募方法 完全マニュアル
ミラーレスカメラにピッタリ!広角レンズの選び方
写真愛好家必見!大三元レンズの魅力とは?
オールドレンズの楽しみ方
稼げるレンズはこれだ
プロカメラマンを目指すならどのレンズを購入すればいい?
単焦点レンズのメリット・デメリット
■今後追加予定の記事
目的別レンズの選び方
カメラメーカー純正レンズがおすすめの理由
Z TELECONVERTER TC-1.4x テレコンバーター レビュー
NIKKOR Z 20mm f/1.8 S レビュー
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S レビュー
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR レビュー
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR レビュー
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED レビュー
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G レビュー
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR レビュー
PC NIKKOR 19mm f/4E ED レビュー
メニュー
Nikon Z9 レビュー
Nikon Z8 レビュー
Nikon D6 レビュー
Nikon Zfc レビュー
Nikon Zfの噂
Nikon Z30 レビュー
Nikon Z6ii レビュー
ニコン レンズ レビュー
Nikonカメラマンのコラム
新着記事
2025/7/1 Nikon Z8 ファームウェア アップデート方法
2024/6/23 ニコン キャッシュバックキャンペン夏(2024/6/28〜8/26)
2024/4/19 NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR 開梱レビュー
2024/3/28 NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レビュー
2024/3/13 ファームウェア Ver5.00、進化し続けるNikon Z9
2024/1/2 2023年、買って良かった写真機材TOP10
2023/8/20 Nikon Z8 リコール発生!それでもNikonを信じ続ける理由。
2023/7/12 Z6ii、Z7iiの最新ファームウェア Ver. 1.60が公開された。
2023/6/13 Nikon Z9、ファームウェア Ver4.00、どこまで進化し続けるのか【更新】
2023/6/2 実録!Nikon Z8での長時間撮影、バッテリーの持ちを徹底検証 [UPDATE]
2023/5/26 Nikon Z8、開封、開梱、UNBOXING レビュー
2023/5/24 Nikon Z8活用ガイド(PDF版)(操作マニュアル)が公開されました
2023/5/15 プロが教える、Nikon Z8のカスタマイズ設定方法
2023/5/14 Nikon Z8 vs Z9を徹底比較! [UPDATE]
2023/5/14 Nikon Z8 vs D850 スペック比較
2023/5/13 Nikon Z8、連続撮影枚数、バッファフル枚数
2023/5/13 Nikon Z8 YouTube動画まとめ [UPDATE]
2023/5/12 Nikon Z8 購入・予約完了報告
2023/5/11 Nikon Z8をいち早く体験!先行体験会の全てをレポート
2023/5/11 Nikon MB-N12 パワーバッテリーパック レビュー
2023/5/10 Nikon Z8外観写真(高解像度写真あり)
2023/5/10 ニコン、値上がり一覧表、値上額、値上率のまとめ(2023/5/10)
2023/5/10 Nikon Z8の最新リーク写真を検証
2023/5/9 Nikon Z8、韓国の電波機器認証機関に登録されたことを確認
2023/5/9 Nikon Z8 vs SONY α7R V スペック比較
2023/5/7 Nikon Z8 vs Z7ii スペック 比較
2023/5/7 NIKKOR Z 85mm f/1.2 S レビュー [UPDATE]
2023/5/5 Nikon Z8 vs Z6ii スペック 比較
2023/5/4 プロが教える、Nikon Z6iiのおすすめカスタマイズ設定 [UPDATE]
2023/5/3 Nikon Z8 vs Z9 スペック比較
2023/5/3 サブカメラの必要性:サブ機の活用法やメリット
2023/5/3 サブカメラの選び方
2023/5/3 Nikon Z8 発売が待ち遠しい!Nikon Z8レビュー
2023/4/23 Nikon MC-N10リモートグリップを3ヶ月使ってみた!レビュー
2023/4/23 Nikon MC-N10、SmallRigアタッチメント 開梱レビュー
2023/4/22 職業カメラマンが車を持つメリット、デメリット
2023/4/21 NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S レビュー
2023/4/21 NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 vs 70-200mm f/2.8を比較レビュー
2023/1/5 NIKKOR Z 85mm f/1.2 S 外観レビュー
2023/1/3 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S、仕様・スペック 徹底レビュー
2022/12/31 2022年、買って良かった写真機材TOP10
2022/11/10 NIKONキャシュバックキャンペーン 2022秋冬がお得すぎる件
2022/11/2 Nikon Z9、即納在庫あり速報 【2022/12/31 即納在庫あり】
2022/10/26 Nikon Z9、ファームウェア Ver3.00、進化が止まらない【更新】
2022/9/2 Nikon Z9、バッテリーの持ち
2022/9/1 Amazonで購入予約したNikon Z9がキャンセルされてしまった件
2022/7/6 Nikon Z9 ファームウェア アップデート2.10でさらに進化した
2022/6/29 Nikon Z30 YouTube 動画
2022/6/29 Nikon Z30 レビュー
2022/6/29 Nikon Z30 外観 レビュー
2022/6/14 電子シャッターのメリット、デメリット
2022/6/11 NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S レビュー 【作例あり】
2022/6/9 運動会撮影に最適なレンズとは?NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRで最高の思い出を残そう
2022/6/8 NIKONキャシュバックキャンペーン 応募方法 完全マニュアル
2022/5/24 NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR レビュー
2022/5/8 RRS CA-1 ケーブルアンカー レビュー
2022/5/6 Nikon Z9用 おすすめ Lブラケット比較(SmallRig、Kirk、RRS)
2022/5/4 Nikon Z9 用 RRS Lブラケット (L型プレート) レビュー
2022/4/23 Nikon Z9、Ver.2.0のバグ?連続撮影すると一部コマにレンズ歪曲収差が残ったままになる
2022/4/22 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S レビュー
2022/4/20 Nikon Z9、ファームウェア Ver2.00の進化が凄い
2022/4/14 【更新】Nikon Z9、YouTubeレビュー動画 まとめ
2022/1/28 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S、開梱レビュー
2022/1/28 24-70mm vs 24-120mm vs 24-200mm を比較
2022/1/28 【更新】Nikon Z9の納期、出荷状況の最新情報
2022/1/26 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S レビュー
2022/1/25 【更新】Nikon Z9 ポジティブレビュー。ここが凄い、素晴らしい!
2022/1/23 プロが教える、Nikon Z9のおすすめカスタマイズ設定
2022/1/19 Nikon Z9 がっかり、ここが残念、ネガティブレビュー
2022/1/4 Nikon Z9の製造番号、シリアル番号情報
2021/12/14 Nikon Z9 液晶保護フィルムレビュー
2021/11/14 Nikon Z9 ファーストインプレッション
2021/11/2 Nikon Z9、購入・予約報告
2021/10/28 Nikon Z9、高解像度外観写真
2021/10/28 Nikon Z9、スペック
2021/10/27 Nikon Z9 最新情報
2021/10/27 Nikon Z9 ティザー動画第四弾、ブラックアウトフリー、ファインダー遅延ほとんど無し
2021/10/20 Nikon Z9 ティザー動画第三弾、AF追従がすごい、車AF、バイクAF機能あり
2021/10/13 Nikon Z9 ティザー動画第二弾、動画撮影30分の壁を越えた
2021/10/5 Nikon Z9 ティザーサイト、キターーーーー!
2021/8/19 EN-EL18d Nikon Z9バッテリー レビュー
2021/8/13 Nikon Z9のコードネームはN2014
2021/7/30 Nikon Z9の背面写真、背面液晶モニターはチルト式
2021/7/17更新 Nikon Zfc YouTube動画【続々と動画が追加されています】
2021/7/13 Nikon Z9への要望
2021/7/4 Nikon Zfc vs FUJIFILM X-T4を比較レビュー
2021/7/1 Nikon Zfc vs Z50を比較レビュー
2021/6/29 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S、開梱レビュー
2021/6/29 Nikon Zfc レビュー [NEW]
2021/6/12 Nikon Z6ii、7ヶ月使って分かったポジティブレビュー。ここが凄い、素晴らしい! (更新)
2021/6/12 Nikon Z6ii がっかり。7ヶ月使って分かったネガティブレビュー (更新)
2021/6/5 NIKKOR Z MC 105mm vs NIKKOR Z MC 50mmを比較
2021/6/4 NIKKOR Z MC 105mm vs AF-S MICRO-NIKKOR 105mmを比較
2021/6/4 NIKKOR vs CANON 最新中望遠マイクロレンズ比較
2021/6/3 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR SのYouTube動画一覧
2021/6/2 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S レビュー
2021/6/2 NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 レビュー
2021/5/24 カメラを落としただけなのに
2021/5/20 NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S レビュー
2021/5/5 Nikon Z9、サイズ予想、サイズ比較
2021/5/5 Nikon Z6iiのAF性能、長期使用レビュー
2021/4/30 Nikon D6 vs Z6iiを比較
2021/4/28 Nikon Z8の噂
2021/4/26 Nikon Z6ii、サルでも分かるファームウェアアップデート方法
2021/4/19 Niokn D6、ファームウェアアップデートを行う方法
2021/4/13 Nikon Z9 vs Canon EOS R3を比較
2021/4/6 Nikon Z9を購入する理由とは
2021/3/28 Nikon D6、Err表示の対処方法とは?
2021/3/22 ダブルスロットのメリット、デメリットを徹底検証
2021/3/14 Nikon Z9 vs D6を比較、大きさ比較
2021/3/11 縦位置グリップのメリット、デメリット
2021/3/10 Nikon Z9、スペック 予想
2021/3/10 NIKON Z9 妄想レビュー
2021/1/24 NIKKOR Z 50mm f/1.2 s レビュー